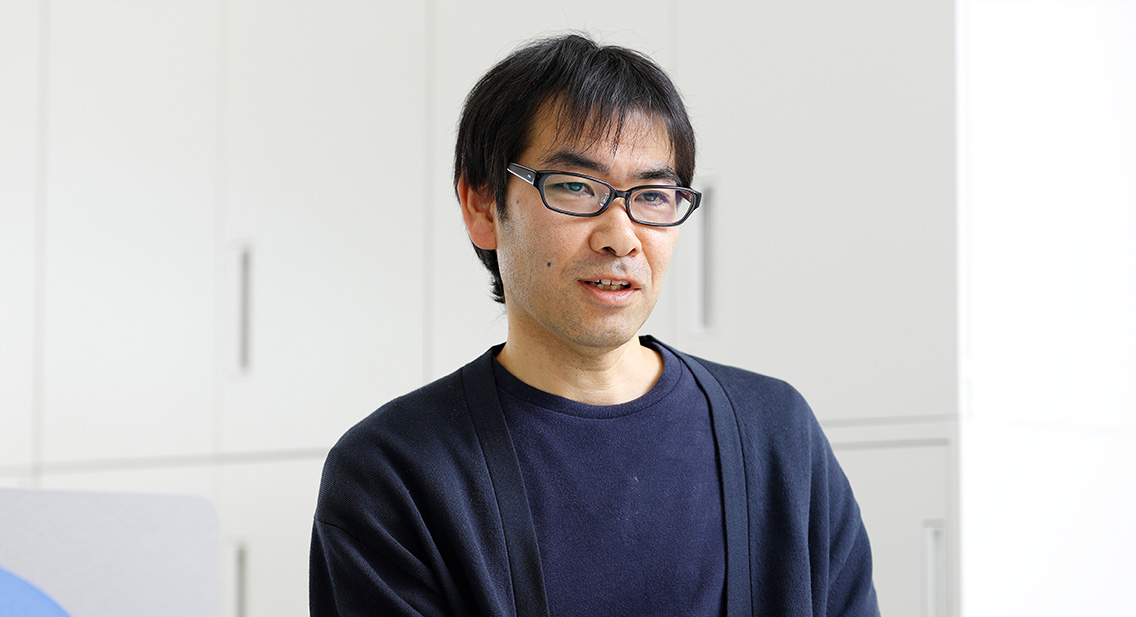
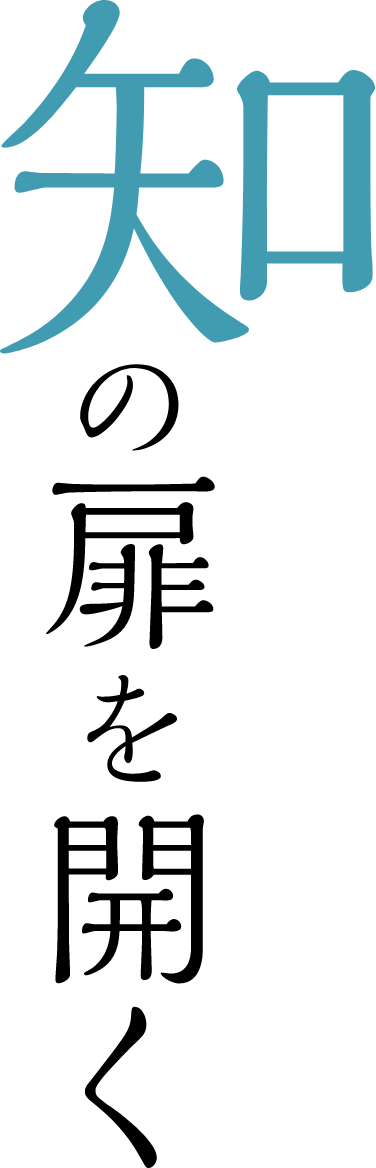
光機能ナノカーボンを精密設計し、合成の力で自在に組み上げる
精密に分子設計して最高にかっこいい分子を合成する
次世代の新材料として期待されているナノカーボンは、多数の炭素(C)原子が結合したナノ(10憶分の1)メートルサイズの同素体です。その立体構造はさまざまで、サッカーボールのような球状の「フラーレン」のほか、円筒状に巻いた「カーボンナノチューブ(CNT)」、1原子の厚みで平面に広がる「グラフェン」が発見されています。それぞれの構造パターンにより、熱や電気の伝導、光の吸収、発光、機械強度などに桁違いの機能を発揮し、しかも、炭素材料は軽くて柔軟なことから、電子部品など幅広い用途を目指して盛んに研究されています。
荒谷教授は、芳香族分子のピースを図形パズルのように、有機合成の力で目的のナノカーボン構造に組み上げるボトムアップ手法により、相次いで新しい機能をもつ物質を生み出してきました。
通常の工業生産では、原料の黒鉛などを熱して炭素を気化させ、それを凝縮して多種の立体構造をもつ物質を得ますが、「そのようなナノカーボン材料は、複数の構造が混在しているので、単一の性質を示さない。単一構造をもち優れた機能に特化したナノカーボンを精密に作り出したい。そのために、設計段階から大きな分子に組み上がった時の機能を予測して、出発点の炭素分子と合成ルートを選択します。最高にかっこいい分子を世界に送り出したい」と荒谷教授。
大容量の立体ナノカーボン
ナノカーボンの特徴は、炭素原子6個が正六角形に結合した「ベンゼン」という分子がつながり合い、ハチの巣のような網目構造を形作っていることです。このハチの巣の面内を自由に移動できる電子(パイ電子)を備えているので、導電性などに優れているのです。
荒谷教授は、複数の「ベンゼン」を結合した多環芳香族化合物から合成をスタートします。これまでの目覚ましい成果の一つは、炭素原子60個が結合した大きな分子の代表であるフラーレン(直径約1ナノメートル)を、さらに上回る直径3~4ナノメートルの立体ナノカーボンの有機合成に短工程で成功したことです。正六角形が13個結合したパネルのような平面構造を形成する「ヘキサベンゾコロネン」という分子を組み合わせて作りました。
一般に有機化学の研究に使われている人工の有機分子に比べて5倍以上の大きさです。有機分子は大きくなるほど溶けにくくなるので、あらかじめ分子に可溶性の置換基を結合するなど工夫を重ねました。荒谷教授は「現在、この大きな化合物に、フラーレンなどの物質を認識して取り込む機能を持たせ、その中に入った物質の性能を引き出す研究を進めており、さらに一回り大きな分子を開発しています」と語ります。
構造の非対称化が“異常な”光の吸収能を導く
また、荒谷教授は、ベンゼン2個が結合した「ナフタレン」の構造異性体である「アズレン」が、小さな分子サイズにもかかわらず紫外領域から可視光にいたる長波長まで光を吸収することに注目しています。短波長の紫外光しか吸収できず無色であるナフタレンに対して、同サイズのアズレンは新たな色素を合成する画期的な出発物質になることが期待されます。
アズレンは七角形と五角形の2種の環状化合物が一辺を共有する形で縮環した非対称の分子で、正六角形のベンゼン2個が縮環して対称性が高いナフタレンとは、全体の炭素の個数が同じでも性格が大きく異なります。荒谷教授は「炭素一つの位置の違いで非対称の異方性が分子内を自由に移動するパイ電子を偏在させ、吸収する光の波長の幅を広げることがとても面白い」と感じています。このような非対称の炭素化合物の中には未だ隠れた機能があると見られ、荒谷教授は、得意の縮環反応を操りアズレンをナノカーボンに融合して調べる研究を重ねています。
大きさの限界を突破したい
「最新有機化学の手法を駆使して限界を超えた大きさのパイ共役系分子の合成に挑戦し、その時、どのような物性が出現するか確かめたい」と有機化学研究者としての究極の夢を語る荒谷教授。中学生のときの化学実験の授業で物質の化学変化の面白さ、モノづくりの楽しさを知ったことから、一途に有機化学研究の道を進みました。京都大学大学院生時代は、人工光合成をテーマに、クロロフィル(葉緑素)の誘導体を配列して巨大分子化し、光を捕集するアンテナ機能を増強する研究に取り組みました。
「自分が面白いと思うことを学生と一緒になってとことん追求する。それができるのが大学です」と荒谷教授は、男女関係なく理科好きの学生が増えて社会で活躍できるよう、ワクワクしながら実験できる研究テーマを日夜考えています。
研究環境には常に気を配っています。かつての有機化学の研究室といえば、有機溶剤などの匂いが立ち込める中、発火の恐れのある試薬などを扱うことがありましたが、実験室はドラフト(局所排気装置)など完備し、極力安全性の高い試薬や設備に切り替え、クリーンな環境を実現しました。また、特に化学分野では、実験記録には伝統的に紙のノートを使うのが当たり前でしたが、本学のDX化推進に伴い他大学に先駆けて電子ラボノートを導入しました。実験室の備品にもこだわり、ラボコートの色としてはちょっと変わったネイビー(濃紺)に揃えています。
研究一途の荒谷教授ですが、自宅では中学受験を控えた長男につきっきりでサポートしているそうです。
高効率のりん光発光材料を目指して
大山助教は、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の博士研究員として研鑽を積み、昨年5月に本学に着任しました。新たに立ち上げたテーマは、光エネルギーを吸収し、高効率でりん光を発する、希少金属を含まない「室温りん光材料」の開発です。りん光は蛍光に比べて発光時間が長く、エネルギー利用効率が高いため、省エネやカーボンニュートラルの観点から注目されています。現在では、有機EL素子などにも使われており、その応用範囲は広がっています。
大山助教は「未だ少ない赤色や近赤外のりん光を発する有機材料の開発に挑戦しています。さらに、長波長でエネルギーの低い近赤外光を外部刺激としてりん光を発生させる手法も確立したい」と抱負を語ります。
このため、新たな研究手法の開発にも挑戦しています。
一般的なりん光発光プロセスでは、分子が光を吸収すると、基底一重項状態 (S0)からS0→Sn→S1→T1と遷移し、励起三重項状態 (T1)からりん光が放出されます。しかし、この過程ではエネルギーロスが多いため、発光効率が低下してしまいます。そこで大山助教は、これまで見過ごされていたS0状態から直接Tn状態へと分子を光励起する手法に注目しています。この手法により、エネルギーロスの多い遷移プロセスを省略し、高効率なりん光発光の実現を目指しています。
「OISTでは発光メカニズムの異なる発光材料の研究に取り組んでいました。自分を成長させるために、常に新しいことを習得し続けたいと考えているので、本学で新たな方向性の研究ができることを嬉しく思っている」と話します。夢は「自分の研究成果が中高の教科書に掲載され、それをきっかけに理系を志望する学生が増えること」です。

大山 諒子助教
失敗しても、次の成功につなげる
博士後期課程3年生で、インド出身のアムルタ・マノジ・レナさんは、精密に設計した有機分子から自己集合超分子ポリマーを組み上げ、その上に多数の量子ドットを1次元配列する画期的な手法を開発し、量子ドット単体では出せない発光特性を調べる端緒をつかみました。「基礎研究はほぼ終了し、応用段階に入っています。奈良先端大への留学は、出身大学の指導教員の薦めで、研究に特化していてとても早く結果が出せました。これからも大学で研究を続けたい」と話します。モットーは「何度失敗しても、次の成功につなげる」。研究も人生も同じだそうです。
博士前期課程1年生の平川美穂さんは、荒谷教授が精力的に研究を進めている色素“アズレン”の新しい誘導体の化学合成にわずか半年で成功し、その長波長の光吸収特性について学会で発表しました。「ひとの目に見えない近赤外光を吸収する有機分子の世界記録を塗り替えたい」と意欲を見せます。高校の授業で学んだ有機化学が「パズルのようで面白い」と思ったのがきっかけで研究の道に進みましたが、大学学部までは化学合成の経験がなく「とにかくわからないことは何でも聞き、フィードバックされた情報により知識を深める。本学の先生方や先輩のサポートには大満足」と話します。日々の研究活動が楽しく博士後期課程への進学も決めた平川さんの趣味は、ロックダンス。ダンスバトルにも参加しています。

アムルタ・マノジ・レナさん

平川 美穂さん
機能有機化学研究室はヨビノリたくみ氏による物質創成科学領域の紹介動画にも登場しています。是非ご覧ください。




